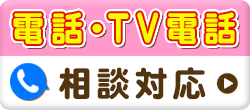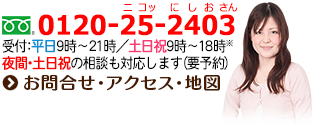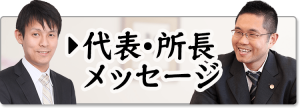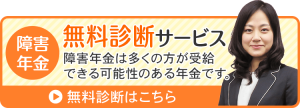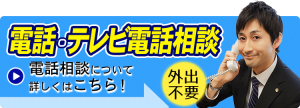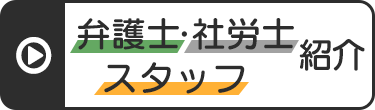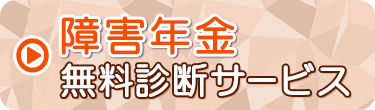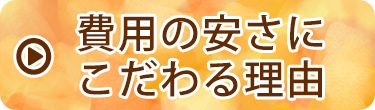白血病で障害年金が受け取れる場合
1 障害年金認定基準の中の位置づけ
白血病は、障害年金の認定基準の中では、血液・造血器疾患による障害に位置付けられています。
血液・造血器疾患は、3種類に大別されており、再生不良性貧血や溶結性貧血等の赤血球系・造血不全疾患が1種類目、血小板減少性紫斑病や凝固因子欠乏症等の血栓・止血疾患が2種類目であり、白血病は悪性リンパ腫や多発性骨髄腫等とともに白血球系・造血器腫瘍疾患として3種類目に分類されています。
2 認定基準の判断枠組みについて
白血病を含む白血球系・造血器腫瘍疾患では、以下の3つの観点を組み合わせて、障害の程度を評価する仕組みが採用されています。
1つ目の観点が、臨床所見です。
これは、認定基準では「A表」というものにまとめられており、例えば、発熱や貧血、易感染性、輸血の要否等が記載されています。
2つ目の観点が、検査所見です。
これは、認定基準では「B表」というものにまとめられており、例えば、血中のヘモグロビン濃度や血小板数、正常好中球数、正常リンパ球数といった検査指標がどの程度の数値になっているのかを確認することになっています。
3つ目の観点が、一般状態区分表によって5段階で評価される日常生活や就労の制限の状況です。
例えば、一番軽い「ア」は、無症状で特に制限なく日常生活やできる状態をいいます。
反対に、一番重い「オ」は、いわゆる寝たきりのような状況をいいます。
そして、この間に、「イ」~「エ」の3段階で、軽労働が可能な程度から、就労不能で日常生活は少しの介助で過ごせる程度、しばしば介助が必要な程度というように評価が分かれていきます。
白血病での障害年金の等級の認定はこれらの3つの観点の組み合わせで行われ、例えば、臨床所見においてA表のⅡに列挙されている臨床所見が1つ以上あり、B表ではⅡに該当する検査所見(ヘモグロビン濃度等が所定の数値の範囲にあるかで判断します)が1つ以上あり、一般状態区分表のエ又はウに該当する場合には、2級に該当することとなります。
同様にA表Ⅰに列挙されている臨床所見が1つ以上あり、B表Ⅰに該当する検査所見が1つ以上あり、一般状態区分表のオに該当する場合には、1級に該当することとなります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 障害年金の申請期間
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の時効
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 学生でも障害年金の支給を受けられるのか
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金を受給すると扶養からはずれるのか
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 統合失調症で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- 発達障害で障害年金が受け取れる場合
- ダウン症で障害年金を請求する場合のポイント
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 呼吸不全で障害年金を請求する場合のポイント
- 肝炎で障害年金を請求する場合のポイント
- 白血病で障害年金が受け取れる場合
- クローン病で障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金の更新
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒601-8003京都府京都市南区
東九条西山王町11
白川ビルⅡ4F
0120-25-2403